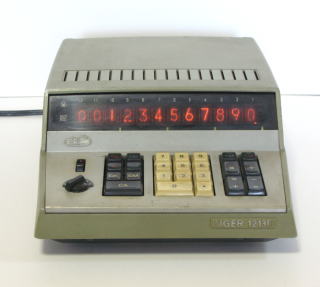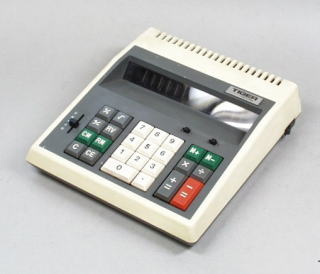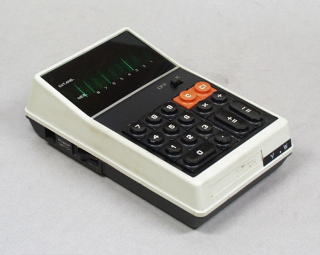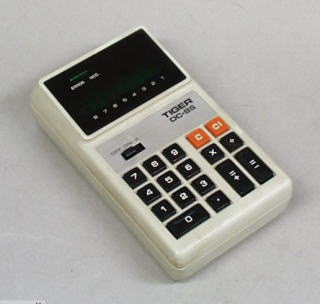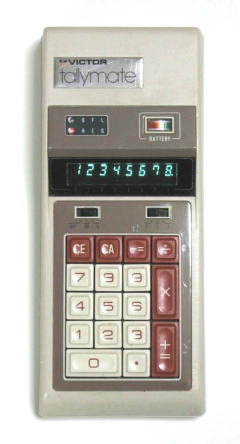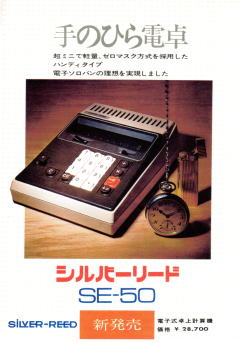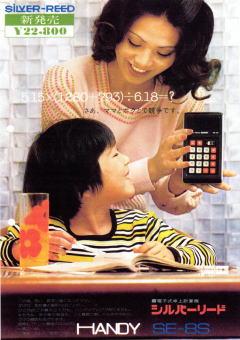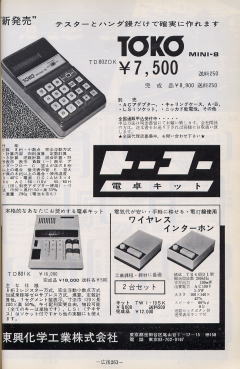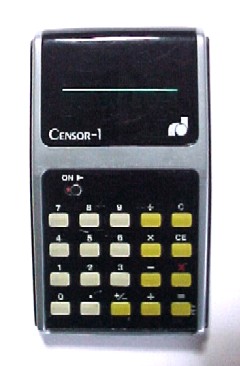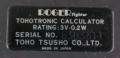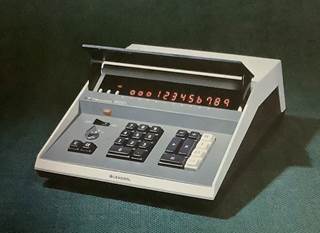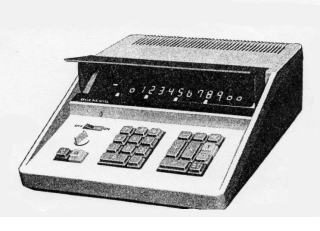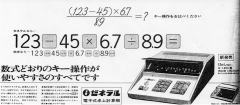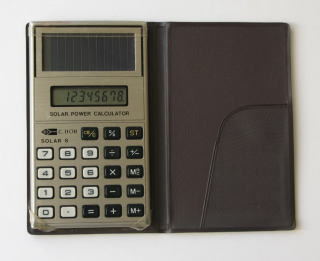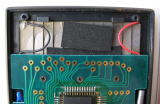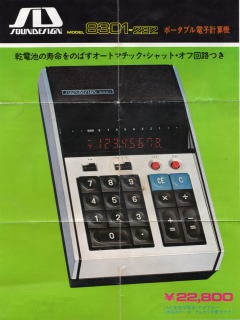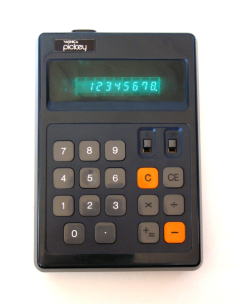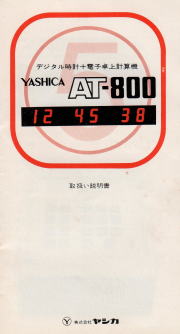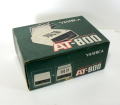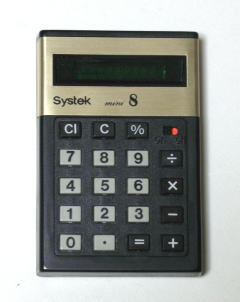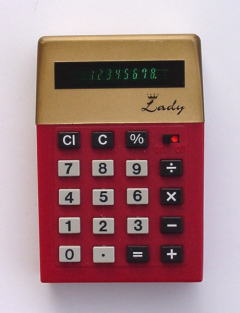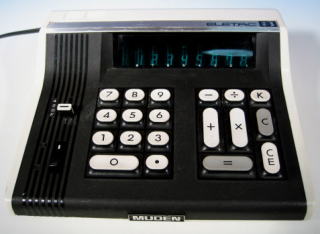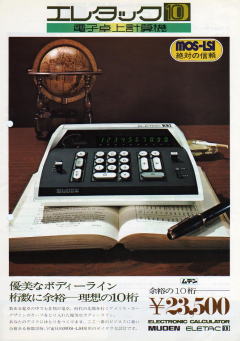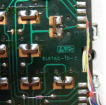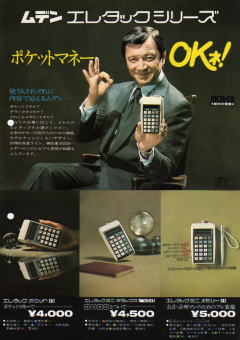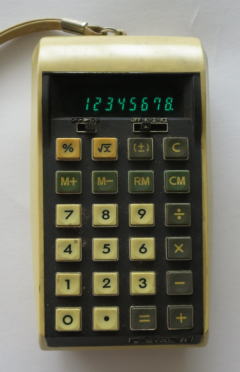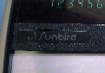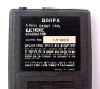|

|
|
�^�C�K�[�v�Z��
�^�C�K�[�͋@�B���v�Z�@�Ŏs������[�h������Ђł���B�������A���{�v�Z�@���r�W�R���ЂƂ��ēd�앪��ϋɓI�ɓW�J�����̂ɔ�ׁA���Ђ͓d��ւ̈ڍs���x�ꂽ�B
�����́AANITA,�J�V�I�Ȃǂ������������d���̔������肵�����A���̌�͋Z�p�v�Z�p�ŗD�ꂽ���\�������H�ɁETI�EHP �Ȃǂ̓d���̔��������A�^�C�K�[�u�����h�ɂ��OEM ���������Ђ̔̔��ԁi���́j�Ŕ̔������肵���B
|
|
|

|
�^�C�K�[1213 (�^�C�K�[�v�Z��)
1970�N2�����������ꂽ�ŏ��̃^�C�K�[�u�����h�̓d��B
�����͓��ʍH�B
���ʍH�͎�Ƃ��ēd�b�������Ƃ��������A�����f�W�^���@�핪��ւ̎Q��������ɁA�����A�������������d�앪��ɂ����Đi�o�����B���Ђ͂قǂȂ��d�앪�삩��P�ނ��邱�ƂɂȂ邪�A�d�앪��œ����Z�p�͂ɂ����Ƃ�POS����ɎQ�����A�听�������߂��B
�����̉��i��137,000�~�B
�����͓��{�ʐM�H�Ɗ�����ЁB
���d�q�Ȋw1970�N7�����L��
|

���{�o�ϐV�� 1970.2.10.
|
|
|
|
|
|
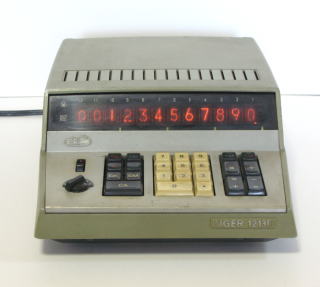
|
�^�C�K�[1213D (�^�C�K�[�v�Z��)
1970�N�Ƀ^�C�K�[���甭�����ꂽ�d��B���{�ʐM�H�Ɗ�����Ёi���ʍH�j�ɂ��OEM�d��B
1213D�Ə̂��A1213 �ƊO�`�E�@�\���قړ���B
SSI �̃��W�b�N�ɂ���H�\���A�������̂́i�����j�P�O�O�E�Q�O�OV �ؑւ����Ă���A�����A�o������ɓ���Ă������Ƃ��킩��j�B
W 245 x H 117 x D 342 �o 15�� Ƹ�������
1970�N11�������B
|
|
|
|
|
|

�j�@�H�[�V��

Photo courtesy : Mr.Toshiro Hata
|
�^�C�K�[1213E (�^�C�K�[�v�Z��)
1971�N�ɔ������ꂽ�d��B���ʍH�����OEM �ōŌ�̌`���B
�@W 180 x H 74 x D 258 �o�B�O�H��
MA8149 �`8154�̂U���� ��� �ō\���A8��
�V������ �ԐF���d�ǁB
�̔��� �V������ �́u�O�v�\���� ���̐����Ɣ�ׂāu�ǂ݂ɂ����v�Ƃ̐������������Ƃ��甼���́uo�v�ɂ���悤�A�^�C�K�[����t����H����荞�݁A���������肵���B
1971�N�����B
�����̉��i��68,000�~�B
|
|
|
|
|
|
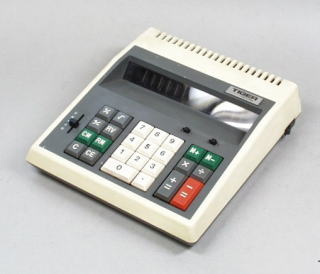
�o�T�j�@�H�[�V��
|
121RS
(�^�C�K�[�v�Z��)
DOS�p�\�R���̏��� ��p�ő����̒������[�J�[����|�����悤�ɁA���� ���{�Łu�l�������[�J�[�v�ƌ���ꂽ�H��ŁA1973(S43)�� �O�^ �P�Q�PR �Ƃ͕ʍH���OEM�������̂ł���B
�O�H�� �P���� M5867-21B �g�p�A10��
�u���X�����āAW 212 x H 67 x D 240 �o
|
|
|
|
|
|
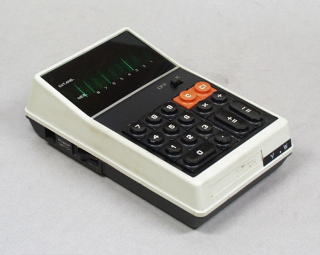
�o�T�j�@�H�[�V��
|
DC-08
(�^�C�K�[�v�Z��)
�u���U�[�H�Ƃ����OEM�ɂ��ŏ��̋@��B�Z�F���������Ђ̂Ƃ�܂Ƃ߂��s�����B
TI �� �P���� TMS0105BNC �g�p�i���������̃��[�J�[�ō̗p�j�W������ iToron�i�ɐ��d�q�j8�ӒP��
|
|
|
|
|
|
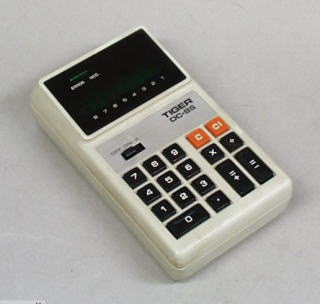
�o�T�j�@�H�[�V��
|
DC-8S
(�^�C�K�[�v�Z��)
�^�C�K�[�v�Z�@���1973�N2���ɔ������ꂽ�|�P�b�g�d��B
DC-8SA�Ƃc�b�|�W�r�` �� �P�OX 5�d�r��p���A�j�b�J�h�[�d�d�r�i�P�OX 5 �߯��j��p�@�ɂȂ������́A�W�r�`�ƕ��s�̔����ꂽ�B
1973�N�B
32,500�~�B
|
|
|
|
|
|

|
DC-8SA
(�^�C�K�[�v�Z��)
1973�N2���ɔ������ꂽ�d��B������ DC-8S (32,500�~�j���������ꂽ�B
�Z�F�����̒���Ńu���U�[�Ђ��^�C�K�[�v�Z�@�ɂn�d�l�������ꂽ���́B
DC-8SA�́A�����Ƃ��Ă͐�[�I�ȃL�[�{�[�h�@�\�i��V���R���S���Ɣ�ڐG�U���j���̗p���Ă���A�P�R�d�r���T�{�g�p���B�����ɂ͓����Ɠ��Ő��̃`�b�v���g���Ă���B�����̉��i23,700�~�B
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Tallymate (No.1) (Victor Comptomater)
�č��V�J�S�̂u�����������Ђ��甭�����ꂽ�d��B�M�a�f�B�W�^���Ђ�OEM�B
�e�L�T�X�C���X�c�������c�Ђ̃����`�b�vLSI �ATMS-1050���g�p���Ă���B
���{�ł�1971�N�A�č��ł�1973�N�ɔ������ꂽ�B
�����r�W�R���Ђ��琢�E���̃|�P�b�g�d��LE-120A����������b��ƂȂ������ALE-120A�͔��ɍ����������B
����ɑ��A�����N�ɔ������ꂽTallymate �͐}�̂����傫���������̂́ALE-120A �Ɠ��l���d�r���g���A���i��LE-120A �̔��z���������Ƃ���傫�Ȑl�C�����B
�P�R�d�r6�{�Ⴕ����AC�d���g�p�B
|
|
|
|
|
|
|
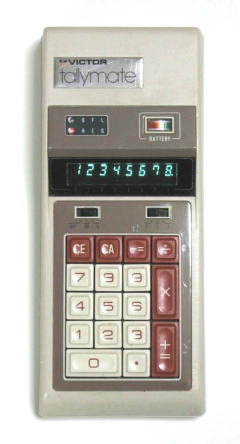
|
Tallymate (No.2) (Victor Comptomater)
Tallymate (No.1) �̐F�Ⴂ�BVictor�Ђ̐F������p���Ă���B
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
U-TAC
TC-8
Tallymate �Ǝ����`��̓d��B�ڍוs���B�d��̍���ɋL����Ă��� "Kobenica" �����[�J�[���ł��낤���B�d�r�{�b�N�X�̂ӂ��ɂ� "U-TAC MODEL: TC-8" �Ə�����Ă���B�������݂�ƁATallymate ���͂邩�ɕ��G�ȍ\���ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��� Tallymate ������������̂��̂Ƃ݂���BCPU �ɂ̓e�L�T�X�C���X�c�������g�Ђ̃`�b�v���p�����A�`�b�v�ɂ�"TMS0105BNC
7245" �ƋL����Ă���B
Tallymate �Ɠ��l���ɉ�������������������f�U�C���̓d��ł���B
|
|
|
|
|
|
�V���o�[���H (Silver Reed)
1952�N�Ɂu�ۉz�ҕ��@�B������Ёv�Ƃ��Đݗ�����A1967�N�Ɂu�V���o�[���H������Ёv�ɕύX���ꂽ�B
�u�V���o�[�ҋ@�v�Œm���邪�A�ƒ�p�@��A�^�C�v���C�^�[�Ȃǎ����@��Ȃǂ��������Ă����B
�{�Ƃ́u�҂@�v��u�^�C�v���C�^�[�v�̎s��k���ɔ����Ɛт͖����I�Ɉ����A2011�N1���ɓ����،������1�����p�~�B
1974�N�����Ŏ����p�@�B�̎戵������50���A�]�ƈ���2200���ōH��͏����s�ɂ������B
|
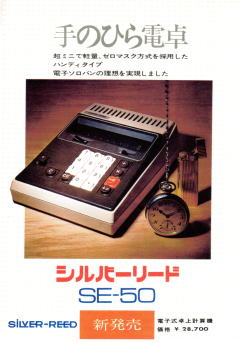

|
|
|
|

|
SE-8K
1973�N�ɔ������ꂽ�n���f�B�^�C�v��8���d��B
�����E�����v�Z�AEX�L�[�ɂ��t���v�Z�A��v�Z�Ȃlj\�ȃr�W�l�X�����d��B
���������_�����B
�I�[�o�[�t���[�\���B
���{���B
22,800�~�B
|

|
|
|
|
|
|

|
Mini �W
���`���B
|
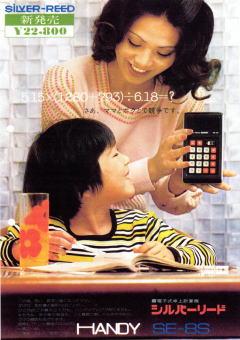

|
|
|
|
|
|
|
|

|
MINI-8
(TD-802D)
�������w�H�Ƃ���P�X�V�S�N�ɔ������ꂽ�W�������`�b�vLSI�d��B�P�R�d�r�S�{�Ⴕ���̓A�_�v�^�[�g�p�B�`�b�v�� TI �А��B8,900�~�B
�g�ݗ��ăL�b�g(TD-802DK)��7,500�~�Ŕ�������Ă����B
�� TOKO MINI-8 �g���w����
|
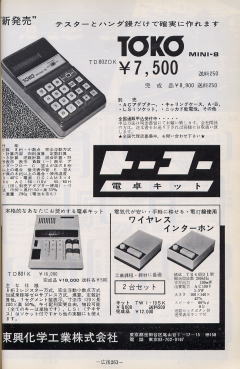
|
|
|
|
|
|
|
|
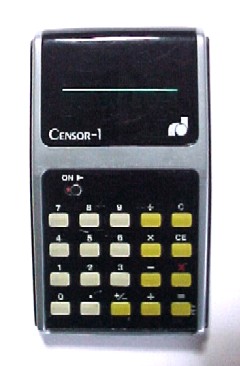
|
Censor-1
�P�R�d�r�Q�{�Ⴕ���̓A�_�v�^�[�ŋ쓮�BNEC �А��̃`�b�v���g�p�B�T�C�h���猩���f�U�C�����Ȃ��Ȃ��悢�B
|
|
|
|
|
|

|
ROGER F-6
12�����d��B�P�R�d�r�Q�{�Ⴕ���̓A�_�v�^�[�ŋ쓮�B
NEC �А��̃`�b�v���g�p�B
���{����������������ƃK���e�[�v�ŕ��i���Œ肷��Ȃǔ��ɎG�ȍ��ɂȂ��Ă���B
|
|
|
|
|
|
�����G���N�g����������
�d�Z�@���Ӌ@��A�����̐����@��A�����̃e�X�^�[�A�������i�Ȃǂ���舵���Ă����B
1974�N�����]�ƈ���200���A�{�Ђ͐V�h�A�S����6�̎x�X�E�c�Ə����������B
|
|
|

|
mark1
80AD (Tokyo Electron)
|
|

|
|
|
|
|
|
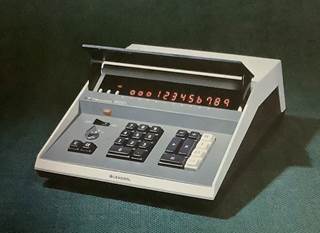
|
TEKNIKA
1200
�[�l�����Ђ�1968�N�ɍŏ��̓d������Ă��邪���ꂪ����ɂ����邩�͕s���B
185.000�~�B
|
|
|
|
|
|
|
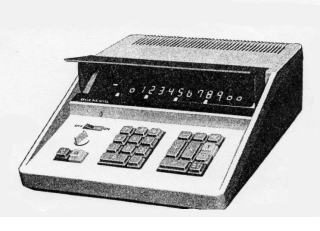
|
G-1201
1970�N�ɔ������ꂽ12��1�������[�d��B
138.000�~�B
|
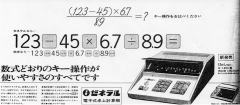
���{�o�ϐV�� 1970.12.3.
|
|
|
|
|
|

|
804
�����̃|�P�b�g�d��B
�[�d�̓N���[�h����ōs���B
�ۊǎ��ɂ͔������̃v���X�`�b�N�J�o�[�����Ԃ���B
�V���A��No.3602�B
���{���B
|
|
|
|
|
|

|
806
�C�O�Ŕ̔����ꂽ���́B
�\�ʂ̃V�[����"TEKNIKA"�̕��������邱�Ƃ���č��E�j���[���[�N�́u�e�N�j�J�Ёv���̔��������̂Ƃ݂���B
�P3�d�r4�{���ɑ�������B
�^�Ԃ�"EDC-806"�B
|
|
|
|
|
|

|
807
�P3�d�r3�{�g�p�B
NEC��CPU�g�p�B
�^�Ԃ�"EDC-807"
|
|
|
|
|
|

|
812
�P3�d�r3�{�g�p�B
�Ԃ�LED�d��B
|
|
|
|
|
|
�ɓ������� (C.ITOH)
1974�N�̃r�W�l�X�}�V�[���Y�E�C���[�u�b�N�ɂ��ƁA���R�[�A���Ńr�W�l�X�}�V���Ȃǂ��玖���@�B���d����̔����Ă����B
|
|
|

|
8005
�������݂�Ƃm�d�b�̕�����ZEBRA�̕����������B
|
|
|
|
|
|
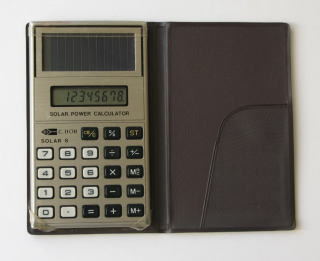
|
SOLAR 8
�����̑��z�d�r���d��B
���a�T���@�d��OEM�d��B
�iV-007 �Ƒ��z�d�r�p�l���̈ʒu�͈Ⴄ�����̑��͓����B�j
���蒠�^�d��
|
|
|
|
|
|
�ۍg�ѓc (Miida)
�ۍg�ѓc�͓��{�Ő��Y���ꂽ�d���Miida�u�����h�ŊC�O�Ŕ̔������B�����̋@���Omron�Ђ�OEM�Ƃ݂���B
|
|
|

|
8
Omron
80 ��OEM �ŁB
�I��������CPU�A�p�i�\�j�b�N�̏[�d�r�Ɠ��ł̔����̂��g���Ă���B���ɂ́A"Miida Electronics,Inc.
17 EMPIRE BLVD, S. HACKENSACK, N.J. 07606"�̋L�q������B�i�����͓̂��{�ň�����ꂽ���́B�j
�V���A��No.01731249�B
|
Omron 80

|
|
|
|
|
�O�䕨�Y
�ۍg�ѓc�����{�Ő��Y���ꂽ�d����C�O�Ŕ̔������̂ɑ��O�䕨�Y�͊C�O�Ŕ̔����ꂽ�d�����{�ɗA�������������B
|
|
|

|
8301
�č�SOUNDESIGN�Ђ����������d����O�䕨�Y�d��̔�������Ђ��A�����̔������d��B
�����d�쎩�͓̂��{�Ő������ꂽ���̂ł���A�A���������̂ł͂Ȃ��č�SOUNDESIGN�Ќ����̗A�o�i�������Ŕ̔��������̂���������Ȃ��B�������[�J�[�͕s���B
�d���X�C�b�`���Y��Ă������I�ɓd�����d�r�̖��ʂȏ����������u�I�[�g�}�`�b�N�E�V���b�g�E�I�t��H�v�𓋍ڂ��Ă���B
�S�̒P�Q�d�r�܂���AC�A�_�v�^�[�g�p�B
760g
115(W)�~190(D)�~45(H)mm
22,800�~
|
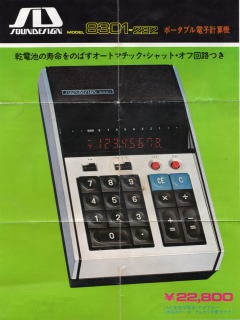

|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Executron 8M
�P2�d�r4�{�Ⴕ����AC�A�_�v�^�[�g�p�B�����͔��ɖ��邭���₷���B�C�M���X�Ŕ̔�����Ă������́BCPU��NEC���B
|
|
|
|
|
|
���V�J (Yashica)
�J�������[�J�[�B1973�N5���ɓd��s��ɐi�o�����B
���Ђ��ŏ��ɔ��������̂́A8���̃n���f�B�^�C�v�́u���V�J�r�b�L�[B800�v�Ə[�d�@�\���t�����u��B800L�v�y�уf�W�^�����v�t�́u���V�JAT800�v��3�@��ŁA���i�͂��ꂼ��23800�~�A29800�~�A49800�~�������B
|
|
|
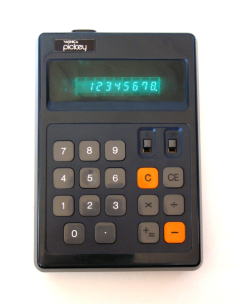
|
Pickey (B800)
1973�N5��20���ɔ������ꂽ���V�J�ŏ��̓d��B
�|�P�b�g�^�̃f�U�C���ŐV���̃m�b�N�^�b�`�L�[���g���Ă���A���������ƌy���ɔ����������ԈႢ�����Ȃ��Ȃ����B
�P�[�X���{�̌`�����Ă���̂������Ă���B
�P�O�d�r�S�{�g�p�B�`�b�A�_�v�^�[���g�p�B
101(w)�~146(D)�~31(H)mm�B
23,800�~�B���{���B
�����ɁA�[�d�@�\�̂���Pickey (B800L)�@(29,800�~�j ���������ꂽ�B
|
|
|
|
|
|

|
AT-800
1973�N6��21���ɔ������ꂽ8���d��B
�ӂ������ƃf�W�^�����v�A�J���Ɠd��Ƃ��Ďg�p�ł���Ƃ����A�ς���̓d��B
���s 166�~�� 150�~�� 72mm�B
�d�� 1.7kg�B
49,800�~�B���{���B
|
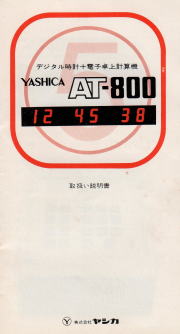

|
|

|
|
|
|
�V�X�e�b�N (Systek)
�V�X�e�b�N�Ђ͓d�앪��ł͂��Ȃ��i�I�Ȋ�Ƃł��������A�d��푈�̍Œ�1976�N���A�|�Y�����Ƃ�����B�������ڍׂ͕s���B
|
|
|
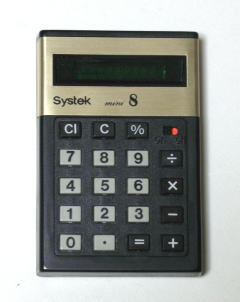
|
mini 8 (Systek)
���ł͔��ɒ������V�X�e�b�N�Ђ̏��^�d��B
�V�X�e�b�N�Ђ͓d�앪��ł͂��Ȃ��i�I�Ȋ�Ƃł��������A�d��푈�̍Œ��P�X�V�U�N���A�|�Y�����Ƃ�����B�������ڍׂɂ��Ă͕s���B����mini 8 �͍����ł͂��܂�݂����Ȃ����A�C�O���[�J�[��OEM���i�͑����o����Ă���B
�P�S�d�r�R�{�g�p�B92�~62�~22mm�B
 ���^�d�� ���^�d��
|
|
|
|
|
|
|
|
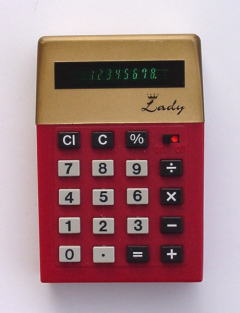
|
Lady (Triumph)
Triumph
�̓h�C�c�̃��[�J�[�BAdler �� Royal �Ђ̊֘A��ƁB
Lady �͏������ӎ��������F�ƐԂ̐F���g����8���̌u���Ǔd��B
Triumph �Ђ͑��ɒj�������̓d�� Sir �����Ă���B
�V�X�e�b�N�Ђ�mini 8 ��OEM�B
|
|
|
|
|
|

|
CO-OP SR-8 (Systek)
�V�X�e�b�N���������S����w���������g���A������������Ȋw�Z�p�p�d�q���v�Z�@�B
���������A���i�͕s�������A���ɂ���V�[������23,800�~���x�������Ɛ��������B
�I���I�t�X�C�b�`�͓��̕����ɂ���B
�P�O�d�r4�{�g�p�B
|
|
|
|
|
|
|
|
���d�e���r�H�� (Muden
televi)
���É��s�ɂ���TV��M�A���e�i�A�g�����V�[�o�[�Ȃǂ������ЁB
���Ђ͓d�q�����v�Z�@�u�G���^�b�N�W�v�i�j�����A�d�앪��ɐi�o�����B

|
|
|
|
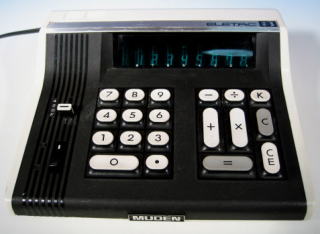
Photo courtesy :Mr.Toshiro Hata
|
ELETAC 8
1972�N11���ɖ��d�e���r�H�Ƃ��ŏ��ɔ��������d��B
19,500�~�B
|
|
|
|
|
|
|

|
ELETAC 10 (MUDEN)
�u����̐�[���s���A�����J�E�J�[�f�U�C���̃J�[�u���Ƃ���ꂽ�D���ȃ{�f�B�[���C���v�������̓d��B
TI�А������`�b�vMOS-LSI���g�p�B
230(W)�~70(H)�~180(D)mm�B1.2kg�B
23,500�~�B
���@�X�y�[�X�G�[�W�f�U�C���f�X�N�g�b�v�d��
|
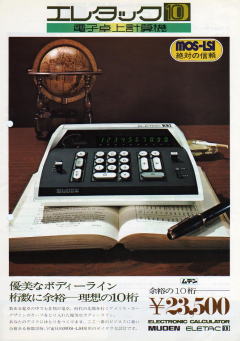
�G���^�b�N10
MOS-LSI�d�l��10���d��B
23,500�~�B
<����>
|
|
|
|
|
|

|
ELETAC
mini DELUXE
�|�P�b�g�T�C�Y MOS-LSI�d��B
�X�g���b�v���{�̏㕔�����ɂ��Ă���B�{�^���͐^�l�p�A�{�̂͗D��ȋȐ��̃��g���ȃf�U�C���̓d��ł���B
�P3�d�r4�{�g�p�B
4,500�~�B
76(W)�~132(D)�~30(H)mm�B
�G���^�b�N �|�P�b�g�d��
|
�G���^�b�N �|�P�b�g8
|
�W���@
|
4,000�~
|
|
�G���^�b�N �~�j �f���b�N�X
|
��x�A%�A�A�}
|
4,500�~
|
|
�G���^�b�N �~�j �������[
|
�������[�v�Z
|
5,000�~
|
|
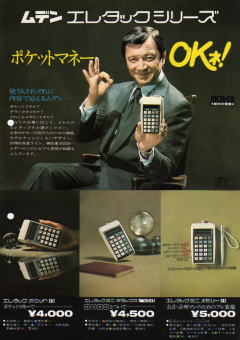
<����>
|
|
|
|
|
|
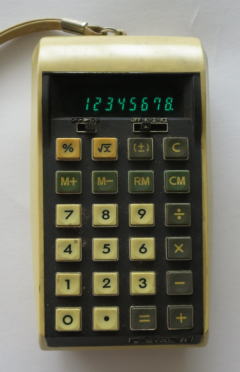
|
ELETAC mini memory
ELETAC
mini DELUXE �Ƀ������[�@�\���t�������́B
�P3�d�r4�{�g�p�B
5,000�~�B
76(W)�~132(D)�~30(H)mm�B
|
|
|
|
|
|
|
�^�}���v���V�X�e�� (TAMAYA TECHNICS INC.)
�]�ˎ���̏���[1975�N�j�ɑn�Ƃ��ꂽ�V�܂̊�ƁB
�����́u�ʉ��v�̏̍��Ŋዾ�̔����肪���Ă������A�������œ_������ۂZ�p�̒~�ς����������삪�ዾ����v����ւƃV�t�g���Ă������B
�d��̍��@�\���A���������i�ޒ��ŁA���Ђ̓V���[�v�Ƌ��͂��čq�@�v�Z�@�\�t���d��������B
���Ђ́A���݂��Z�C�R�[�G�v�\����100��������ЂƂ��Čv���@��̔̔��𑱂��Ă���B
�� �^�}���v���V�X�e���̃z�[���y�[�W
|
|
|

|
NC-77
1978�N�ɔ�������91�N�܂Ŕ̔����ꂽ�q�@�v�Z�iNavigation�j�@�\�t���d��B
�����Ȍv�����s���p��Ƃ��ē����Ƀt�F���g���{�����ؔ��ɓ���Ĕ̔����ꂽ�B
�{�̂̓V���[�v�����������B
���Ђ���͂��̃V���[�Y�Ƃ��āANC-2�ANC-88�ANC-99�ANC-2000����������Ă���B
�� ���d��
|
|
|
|
|
|
���艮 (Sunbird)
�����̓X�[�p�[�����Ѓu�����h�œd��������B
���Ƀ_�C�G�[�����Ѓu�����h�̓d������Ă���B
���_�C�G�[
|
|
|

|
NC6-911
6���\���������L�[���������ƂŌv�Z���ʂ�12���܂ŕ\���ł���B
ON-OFF�L�[�͓��̕����ɕt���Ă���B
�P3�d�r4�{�܂���AC�A�_�v�^�[�g�p�B
|
|
|
|
|
|

|
Sunbird
���ʂɂ��������DT8M�X�P�S�̕������݂���B�V���A��No.000985�B
�����͒P���ȍ\���ɂȂ��Ă���A�hGICO49.8.24."�̃V�[�����\���Ă��邱�Ƃ���1974�N���ł��邱�Ƃ��킩��B
|
|
|
|
|
|
���z�r�W�l�X�}�V�� (GLORIA)
���z�r�W�l�X�}�V���Ђ́A���c��_�c�ɖ{�Ђ�������{�s�ɍH��������Ă����B1974�N�����̏]�ƈ�����48���Ōv�E���Z�@�E�d��A���W�X�^�[�A�G�A�[�|�b�g�̕��i�Ȃǂ����Ă����B
GLORIA �͑��z�r�W�l�X�}�V���Ђ����������d��̃u�����h���B
|
|
|

|
LM-8
GLORIA
LM-8�͐����^�C�v�̓d��B
�[�d���ŏ[�d�r4�{��������Ă���B
|
|
|
|
|
|
|
|
�L�R��
KD-121C
���d�q�Ȋw1970�N7�����L��
|
|
|
|
|
|
|

|
KK-F95
���d��B
�������B
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Astrostar
�o���_�C��Kosmos�Ђ̃��C�Z���X�Ő����̔��������肢�R���s���[�^�BAstro �Ɣ����傫���A�L�[�̌`�Ȃǂ͈قȂ邪�A�L�[�̔z�u����{�I�ȕ����͓����B
|
|
|
|
|
|
|
|

|
800PK
SATEK�Ƃ������[�J�[�i�H�j�����������d��B
���{���B
|
|
|
|
|
|

|