�^�C�K�[�v�Z�@
|
�^�C�K�[�v�Z�@�́A1923�N��{�Ў��Y�ɂ�蔭�����ꂽ�B���̌v�Z�@�͔ނ̖����Ƃ��āu�Ո�v�Z�@�v�𖽖����ꂽ�B�Ո�v�Z�@�̌����͓����̃I�h�i�[���v�Z�@�̌����Ɗ�{�I�ɓ������̂ł��邪�A��{�{�l�����̌v�Z�@�̏��Ă������ǂ����͂킩��Ȃ��B���������͂Q�K���ẲƂ�������قǍ����Ȃ��̂ł������B�Ո�v�Z�@�̊����サ�炭���ČՈ�́uTIGER BRAND�v�ɁA��{�S�H���̓^�C�K�[�v�Z�@���쏊�Ɖ��̂��ꂽ�B�^�C�K�[�v�Z�@�́A���i�̒ቺ�ƂƂ��ɏo�א��������ɑ�����68�N���̃s�[�N���ŔN�ԂS����ɒB�����B�����̓��C�o�����[�J�[���������������A�^�C�K�[�v�Z�@�̒m���x�͔��Q�ő����[�J�[�̂��̂��݂ȃ^�C�K�[�v�Z�@�ƌĂ�Ă����B
|
|
|
|
|

|
�����^18��
1954�N���B�E�_�C��������18���B
|
|
|
|
|
|
|
|

|
H62-20
|
|
|
H62-20�Ɏg���Ă���l�X�ȃp�[�c
|
|
|
|
|

|
H68-21
1968�N�ȍ~���ꂽ�^�C�K�[�v�Z�@�̍ŏI�^�B
�E�_�C��������21���B�A��@�\����������^�C�v�B
�J�o�[��u�����o�[�̓v���X�`�b�N���ƂȂ��Ă���B
|

|
|
|
|
|
|
|

|
H68-S
H68-21�Ɠ�����1968�N�ȍ~�ɐ������ꂽ���́B
H68-21�ƈقȂ�A��@�\�͂��Ă��Ȃ��B
|
|
|
|
|
|
|
�@���{�v�Z�@
���{�v�Z�@�͋@�B���v�Z�@�̎s��Ń^�C�K�[�v�Z�@�ƕ���ő傫�ȃV�F�A�������Ă�����Ƃł���B
�@���Ђ͎����p�@��Ȃǂ��̔����Ă����u���a�m�s�v�̎q��ЂƂ��ď��a17�N�ɐݗ����ꂽ�B�ݗ��������v�Z�@�̌����E����Ɏ��g�݁A���a19�N�Ɍv�Z�@�̍��Y���ɐ��������B���̌�A���Ђ͗l�X�ȋ@��̊J�����s���A���a31�N�ɂ͎蓮���v�Z�@�̌���łƂ�������SM-21 �J�����A����I�Ȕ���グ�����������B�܂��A���a39�N�ɂ�SM-21�^�����ǂ���HL-21 �^�Y�A�̔������B
|
HL-21

|
|
|

|
SM-21
1956�N�ɔ��\�A�̔����ꂽ�B
357(W)�~130(H)�~170(D)mm�B
7.4kg�B
�����̉��i��35,000�~�B
|

|
|
|
|
|
|
PILOT�v�Z�@
PILOT�v�Z�@�́A1961�N�L�[�o�[�v�Z�@���o�h�k�n�s���������Ăł������̂ło�|�P�AP-3�^�������̔����ꂽ�B�����̌v�Z�@�͓����̍��Y�v�Z�@�̒��ōł����^�ł��������Ƃ��炵���Ύ����Ԃɐςݍ��܂ꃉ���[���Z�Ɏg��ꂽ�B
|
|

|
P-3�^
1967�N�ɔ������ꂽ�B�����̉��i��28,000�~�B
|

1967�N3��6�����{�o�ϐV���̍L���B
|
|
�����[���Z�Ɏg��ꂽ���́B
��Ԏԓ��Ŏg�p���邽�߁A�hῂ̈����h���Ă����B
�㕔�ɁuTEAM FALCO�v�Ƃ����l�[���e�[�v���\���Ă���B
|
|
|
|
���Ōv�Z�@
�@�����āu�u���[�X�^�[�v�Z�@�v�����������d�C�i���j�����[�c�Ɏ���ƁB
|
|

�o�T�j�@�H�[�V��
|
���Ł@20-TC
�@�u���[�X�^�[�@�̖ʉe�������c�����v�Z�@�B
�@�����F�u��10���~���_�C����11���~�E�_�C����20���B
�@���@�F �R�S�V�iW)�~�Q�R�S�iH)�~�P�T�Q�iD) �o �B
�@�d��: �V.�X kg�B
�@�����N�͂P�X�U�O�N��̏I��肩��V�O�N��̏��ߍ��Ɛ����B
|
|
|
|
|
|
|
Brunsviga
|
�@�@�B���v�Z�@�̑�\�I�ȃ��[�J�[�B
�@1874�N���V�A�̃I�h�l���͏\�i���u�A�u�����u�A�����J���u���h������p�������̋@�B���v�Z�@�̌��^����邱�Ƃɐ����������A�h�C�c�̃u�����X�r�K�Ђ�1892�N�ɃI�h�l����肱���̓������A��ʂ̋@�B���v�Z�@���s��ɑ���o�����B
|
|
|
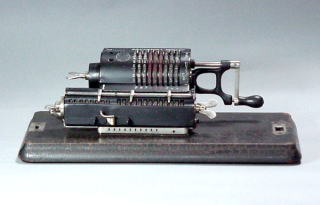
|
Midget
�@����
Midget �́A�h�C�c�ł�Model M �Ƃ������O��1908�N����1927�N�ɂ����Ĕ̔����ꂽ���̂ł���A�č��ł�Midget �Ƃ������O�Ŋv����̃P�[�X�ɓ���̔����ꂽ�B�������ق�
Midget �͕č��R�l�`�J�b�g�B�̃f�B�[���[����w���������̂ł���B
�@�Ƃ���ŁA�^�C�K�[�v�Z�@�̑n�n�҂ł����{�Ў��Y�́A1923�N�ɋ@�B���v�Z�@�����������u�Ո�v�Z��v�Ƃ��Ĕ̔����J�n���邪�A���̍ŏ��̋@��̃f�U�C���͂���Midget �ƍ������Ă���A�v�Z�@�̊J���ɍۂ�����Midget���Q�l�ɂ��ꂽ�Ɛ��������B
|
|
|
|
|
|
|
|

�o�T�j�@�H�[�V��
|
13R
Brunsviga�Ђōł����Y�䐔���������� 13RK�@�̐�s�@��Ƃ݂���B
|
|
|
|
|
|
|
Walther
|
�@�h�C�c�̌��e���[�J�[�B�@�B���v�Z�@�������̔������B
|
|
|

|
WSR 160
�����������{�f�B�[�J���[�A���炩�ȋȐ����A���o�[���E���ɏW������Ȃnjv�Z���s�����ꂽ�@�\���������B
�F�́A���̃p�s�A�O���C�̂ق��݂��������O���C�ƃO���[���̂R�F������B
|
|
|
|
|
|
|
Facit
|
�@�e�`�b�h�s �̓X�G�[�f���̃��[�J�[�B
�@�n�����ɂ̓I�h�i�[�̓������w�������������Ƃ���Ă��邪�A�����Ɂu�I�h�i�[�`���v�����ǂ��A�Ɠ��́u�P�O�L�[ �f�[�^�Z�b�g�v�������J�������B���̕����͍\���㖧���\�ŁA�Ïl���ɗD��Ă������Ƃ���s��Ɏ����ꂽ�B�܂��A�d�����v�Z�@���������������B
|
|
|
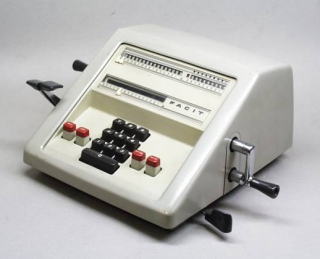
�o�T�j�@�H�[�V��
|
CM2-16
�O�����������i�A���~�n�_�C�J�X�g�j�̋��łȌv�Z�@�B
|
|
|
|
|
|
|
Contina
|
�@�N���^�v�Z�@�̓��_���n�I�[�X�g���A�l�̃N���g�E�w���c�V���^���N�iCurt
Herzstark�j�������������E�ōł��������@�B���v�Z�@�ł���B
�@�ނ̓��_���n�Ƃ������ƂŃi�`�X�ɂ����e���ɑ���ꂽ���A���e���ɂ����Ă��̌v�Z�@�̃A�C�f�A�������������B
�@���C���q�e���V���^�C���̍c���q�����̐v�ɋ����������C�R���e�B�i�Ƃ������c��Ƃ�ݗ����A�u�N���^�v�Z�@�v�Ƃ������O�őS���E�ɐ����̔������B
�@�N���^�v�Z�@�͍ŏ��̌^�iCURTA�j�Ƃ��̌�p�@�iCURTA�U�j���������ꂽ���A���̃��J�j�Y���͊�{�I�ɓ����ŁA���҂Ƃ�11���̌v�Z���\�ł���B
�@�C���^�[�l�b�g�Œ��ׂ�ƁACURTA��1947�N����1970�N�ɂ�����8����ACURTA�U��1954�N����1970�N�ɂ�����7���䂪�����̔����ꂽ�Ƃ̂��Ƃł���B
�@���ɓƑn�I�ȃ��J�j�Y�����������@�B���v�Z��ŁA�d�삪�s���Ȋ��������ł����p�҂����E���ɑ������݂��邷�炵���v�Z�@�ł���B�@
|
|
|

|
CURTA
�@1947�N����1970�N�ɂ��������̔����ꂽ���̂ŁA��8���䂪�o�ׂ��ꂽ�Ƃ����B�������ق̏����i�̃V���A��No�́A56101�ł���A�����1963�N9�����o�ׂ��ꂽ���̂ł���Ƃ̂��Ƃł���B���ɂ��ꂢ�ȏ�Ԃł��邪�A�c�O�Ȃ��ƂɃN���A���o�[���܂�Ă���B
|
|
|
|
|
|
|
|

Photo courtesy : Ms.Misa Kotoya
|
CURTA �U
�@1954�N����1970�N�ɂ��������̔����ꂽ���̂ŁA��7���䂪�o�ׂ��ꂽ�Ƃ����B���J�j�Y���͊�{�I��CURTA�Ɠ�����11���܂Ōv�Z�ł����B
|
|
|
|
|
|
|
|
|

�p���t���b�g�̎ʐ^
|
�������[�d���v�Z�@ (Monroe)
�d���v�Z�@�͎蓮���v�Z�@�Ƀ��[�^�[��t���A�v�Z��Ƃ��ȗ����������́B
�d���v�Z�@����\�I�Ȃ��̂Ƃ��Ă͕č��������[�Ђ̓d���v�Z�@������B
���{�ł͊ۑP�����㗝�X�ɂȂ�A�����ꂽ�B
|
Model
|
���i
|
�@�\
|
|
LA-5-200
|
\252,000
|
�������Z���u
|
|
LA-6-200
|
\308,000
|
������E���Z���u
|
|
CS-10
|
\252,000
|
�������Z���u
|
|
CST-10
|
\280,000
|
�������Z���u
|
|
CSA-10
|
\356,000
|
������E���Z���u
|
|
CAA-10
|
\420,000
|
�S�������u
|
|
|
|
�������[�d���v�Z�@�̃p���t���b�g
|
|
|
|
|
|
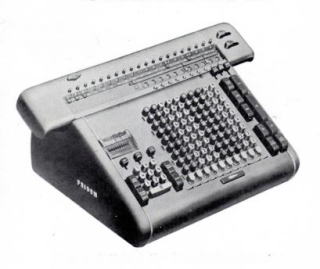
|
STW-10�^
�W���^�@�S�������d�C�v�Z��
�S�������d�C�v�Z�@
|
|
|
|
|
|
|
|

|
SRW�^
�S�������d�C�v�Z��
�������W�J�@�\���t�����B
|
|
|
|
|
|
|
|
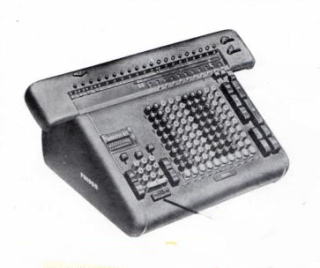
|
ACG�^
�S�������d�C�v�Z��
�L�����[�W���̔C�ӂ̉ӏ��Ŏ����I�Ɏl�̌ܓ����s�����Ƃ��ł���B
|
|
|
|
|
|
|
|

|
SW-10�^
�������d�C�v�Z��
|
|
|
|
|
|
|
|

|
DW-10�^
���������d�C�v�Z��
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
Sensimatics
|
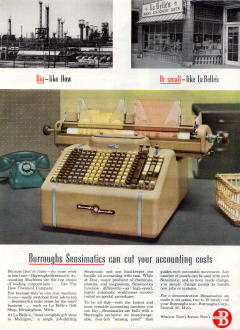
|
|
|
|
|
|
|
|

Photo
courtesy : Mr.Toshifumi Yamamoto
|
Tetractys 24 (Olivetti)
1956�N���������ꂽ�C�^���A�I���x�e�B�Ђ̓d���v�Z�@�B
�ꕗ�ς�����f�U�C�������Ă��邪�A����Ɠ��^�� Divisumma
24 ��MOMA�̉i�v�����i�ɑI�肳��Ă���B
�O���Ƃ͈قȂ�����͔��ɕ��G�ȍ\���ƂȂ��Ă���B
�f�U�C�i�[�� Marcello Nizzoli�B�C�^���A���B
|
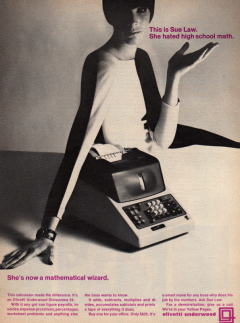
|
|
|
|
|
|
|
Ricomac 211 (RICOH)
|
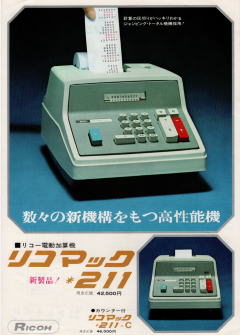

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|